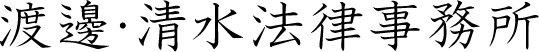第9回 これから留学する人たちへ
後輩の若い弁護士が今年留学することになりましたので、自分の経験も踏まえ、これから留学しようとする弁護士に向けて、ちょっとしたはなむけも兼ねて、自分の思うところを書いてみます。
私は弁護士になって5年目の1992年の夏に留学し、1995年の晩秋に帰国しました。3年半ほど米国にいたことになります。ロースクールに1年、シカゴの法律事務所に2年、ワシントンDCの連邦取引委員会(Federal Trade Commission)という日本の公正取引委員会に相当する政府機関に半年ほど在籍して帰国しました。
40年ほどの前のことですが、当時の日本は、漸く「国際化」(懐かしい言葉です)が叫ばれるようになってきた時代で、私の大学の同級生も、海外に留学したり、海外で勤務したりする人たちが増えてきつつありました。ただ、弁護士の世界は「国際化」など全く進んでおらず、留学経験のある弁護士も、私が所属している事務所でもせいぜい4、5人といったところでした。
もともとアマノジャク系の私は、そういう状況下で、それならオレは留学して数少ない国際弁護士になってやる、という志を持って事務所に入ったのですが、そんな志はあっという間に頓挫します。まず忙しい。文字通り一年365日、朝から深夜まで働き詰めですので、留学準備などしている暇が全くない。また、英語など大学受験以来全く遠ざかっていましたので、英文のレター一通読むのに一日かかる(そういえば過去分詞なんちゅうものがあったなあ、というレベルでした)。その間にも国内事件は山のように降ってくるので、いきおい英語案件は全く進まず、英語案件を振ってくれた先輩弁護士から見放される。逆に国内事件はどんどん面白くなる。事務所に入って3年もするころには、「あ、私は留学はやめました。国内弁護士になります。」などと公言するようになっていました。そんな頃、子供のころから何度も一緒に飲んだ(大きな声では言えませんが)父親の友人が実家に遊びに来るというので出かけていって久しぶりに一緒に飲みました。その席で、「いやー、ぼくはもう留学はやめましたよ。国内事件が面白いので留学する必要もありませんし。」といったところ、「そんな簡単に志を翻すような奴だったのかキミは。」とひどくがっかりされ、情けない目で見られました。アマノジャク系の私、それにまた腹を立て、分かった、それなら頑張って留学してやる、と再び留学志望に復帰し、そして文字通り艱難辛苦の末、2年後に留学することになります。
留学するについて考えたことはたった一つ、留学して帰ってきたらどんな弁護士になるのか(平たく言うと、何を飯の種にするのか)、ということです。上に書いたように、留学を断念していた時期もあったので、留学するときにはもう5年目になっていました。私の所属していた事務所では、当時は7年目ごろからパートナー、要するに共同経営者になるかならないかを考え始める、という年代で、留学せずに国内にとどまっていれば、2年後くらいにはパートナーになる、ならない、という話が出る頃でした。半面、留学に行けば、少なくとも2、3年は日本から離れることになりますので、キャリア的には遅くなる、何より、その間は国内事件の経験を積むこともできません。そのハンデを克服し、というより、それを捨てても得てくるものがなければ留学する意味がありません。そこで、留学によって何を得て帰ってくるのか、そしてどんな弁護士になりたいのか、それを真剣に考えました。
その結果、私が到達した結論が、日米両国で訴訟ができる弁護士になる、そのために留学する、ということでした。
日本の渉外弁護士は、昭和30年代から40年代に留学した先輩たちが先駆けです。彼ら渉外弁護士第一世代の弁護士は、その時期、フルブライトなどの制度を使って海外のロースクールに留学し、帰国後、それまで外国人弁護士の独壇場だった英文契約書作成業務案件にかかわるようになります。ただ、彼らの主な仕事は、端的に言って「横のものを縦にする」、つまり英語で書かれた契約書を日本語に翻訳して(もちろん逆もあります)国内企業の契約締結作業をアシストする、というものでした。(それも、当初は販売代理店契約などのシンプルな契約でしたが、バブル期を経て、日本企業の海外進出のための契約や、ストラクチャード・ファイナンス関連契約などの複雑な契約も処理していくようになります。)そういう渉外弁護士の黎明期を経て、昭和50年代になると、いわゆる渉外弁護士第2世代が登場します。私は彼らを「渉外弁護士ヴァージョン1.2」と呼んでいます。
ヴァージョン1.2の弁護士たちは、縦のものを横にする仕事だけではなく、英米法の概念を日本に輸入して、日本での法律業務に活かすようになります。要するに比較法的アプローチを取り入れて留学経験を日本での実務に活かす弁護士が出てきたということですね。端的な例が、会社法の世界ではデラウェア州の衡平裁判所(Chancery Court)で集積された「経営判断の原則」(Business Judgment Rule)であり、特許法の世界でいえば、連邦巡回裁判所によって編み出された「均等論」(Doctrine of Equivalent)であり、契約法の世界では、いわゆる「表明保証責任」(Representation and Warranty)です。表明保証責任違反を日本法においてどのように構成するかなどの研究も進みました。これらの概念を日本に紹介し、裁判所にも導入させる役割を、渉外弁護士ヴァージョン1.2の弁護士たちが担っていたといえるのです。
ただ、当時私は、ヴァージョン1.2の人たちと同じ事をしようとは思いませんでした。更に進化したヴァージョン1.3の弁護士になりたいと思っていました。そこで目指したのが、日米どちらの裁判所でも訴訟ができる国際訴訟代理人でした。国際訴訟代理人がなぜヴァージョン1.3かというと、そのような弁護士に求められるのは、英米法の概念を日本に導入するだけではなく、まさしく裁判手続の中で、実体法としての英米法と日本法及び双方の訴訟手続を比較し、最適なものを選択する、という能力であり、作業だからです。日米どちらの訴訟法にも精通し、その比較によって裁判地を決め、両国の訴訟手続を縦横に使っていく、そういう弁護士は、日米両国の弁護士のハイブリッドであり、これまでいなかった渉外弁護士の在り方だと考えました。
そのような弁護士になるためには、米国で訴訟の強い事務所で勤務して、実際に訴訟に関与させてもらう必要がありました。そこで、諸先輩にお世話になり、シカゴの超一流の訴訟事務所でインターンをさせてもらうことになりました。そのような弁護士になるのであれば、それ相応の英語力も求められます。私のように語学のセンスも何もない人間は、ロースクール1年間の後、法律事務所で1年間働いたくらいでは、米国での訴訟代理に必要な英語力が身につくとは到底思えませんでした。そこで、密かに、その訴訟事務所では最低2年間働き、日本人とは極力交わらず、英語力を鍛錬することに決めていました
私はそのような目的を定め、米国のロースクールで訴訟手続を重点的に学習し、シカゴの訴訟事務所に就職し、さらに米国独禁法の実務を学ぶために独禁法執行機関の門を叩きました。
当初私は、必要な訓練期間が終わったら日本に帰ってくるつもりでいました。ところが、いざ渡米してみると、アメリカの人たち、そしてアメリカの文化は、予想外に自分のメンタリティに合っていました。無駄な忖度はせず言いたいことは言い合う、そしてお互いどんなに辛辣なことを言い合っても、会話の中に必ずジョークがある、その文化が自分に合っていました(ただ、誤解している方も多いのですが、実はアメリカは日本以上の建前社会です。この点を履き違えると全く受け入れてもらえません。)。シカゴの法律事務所で訴訟を存分にやらせてもらい、国も言語もなく、優秀な弁護士に求められる資質は全く同じであることを実感できるようになった頃には、日本に帰る気は全く消え失せていました。アメリカで弁護士として暮らしていこう、そう思い始めていた頃、国際弁護士会の仕事でやってきた事務所の先輩弁護士とサンフランシスコで会ったときに、その弁護士から「お前は日本に帰ってこないと聞いたぞ。オレが呼び戻しに来たと思っているだろう。違う。おまえのような出来の悪いヤツは要らないから帰ってこなくていい。好きにしろ。」と言われました。アマノジャク系のワタクシ、そういうことなら帰ってやる、と日本に帰ることを決めました。あとで聞くと、その先輩はワタクシがアマノジャク系であったことを把握したうえでかける言葉を決めていたそうで、私はまんまとその先輩の術中にはまったことになります。
そうして帰国したのち、私はその後30年間、国際訴訟を主たる業務として仕事を続けてきました。日本、韓国、アメリカ、オランダの世界4か国で、同時並行で訴訟をハンドリングしたこともあります。英語で喧嘩することも、ある程度はできるようになりました。国際弁護士ヴァージョン1.3になりたいと思っていた私の目的が達成できたかどうかはわかりませんが、良い仕事はしてきたと自負はしています。
自分の話が長くなりました。
今後留学する弁護士には、渉外弁護士ヴァージョン2.0になってほしいと思っています。ヴァージョン1.4でもなく、1.5でもありません。2.0です。その違いは何かというと、これまでの渉外弁護士のヴァージョンアップ弁護士ではなく、全く違った弁護士像を作ってほしいということです。そのために必要なのは恐らく、ハンドリングする業務とクライアントの外延の拡大だと思っています。国際通商でも、ESGでも、AIでも、人権でも、ADRでも、これからの業務の可能性は無限に広がっています。また、クライアントも日本人、日本企業に限定する必要もなく、更には私人ないし私企業に限定する必要もありません。もっと言うと、日本で働く必要もありません。言語の壁を乗り越え、自分の能力と可能性に枠を嵌めず、自由な発想で、これまでの渉外弁護士たちが歩んできた、その経験と知見を踏み台にして、新たな領域にチャレンジして頂きたいと切に願っています。
最後に私が留学するにあたり、先輩弁護士からもらった檄を。
「渉外弁護士には真のスーパースターだけがなれる。」
2023/5/26