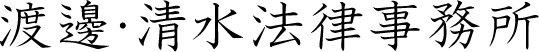第5回 弁護士にとって「正義」とは(その2) ― なぜ弁護士は有罪だとわかりきっている刑事被告人を弁護するのか
先回のコラムでは、正義の相対性について思うところを書いてみました。その中で、法における正義は立場によって異なる、という価値相対論は、至極単純な「正義感」に打ち勝てないこともある、その端的な命題は、「麻原彰晃の弁護をすることは正義に反しないのか」というものだ、と書きました。今回は刑事事件を担当するときの弁護士にとっての「正義」について考えてみます。
よく「何で弁護士は、どうみても有罪に決まっている刑事被告人の弁護ができるのか」と聞かれることがあります。これと似たような文脈で弁護士自身が非常に悩む問題は、事件記録を読んだり被疑者本人と接見したりした限り、弁護士としては有罪としか思えない被疑者が無罪を主張するように依頼してきた場合、無罪を主張する弁護活動ができるのか、より敷衍すれば、自分の確信に反して弁護活動を行うことを強いられた状態で弁護人を続けることができるのか、という問題です。
私自身も、若い頃はこの問題には非常に悩みました。他人を殺し、殴り、あるいは騙し、そしてその結果刑事罰に問われる者がおり、その一方でその被害者がいるときに、加害者と被害者との間の関係を価値相対論で説明することは非常に難しく、そこには厳然たる善悪が存在しているといわざるを得ません(少なくとも私にはそう思えます。)。善悪は相対化できず、悪の化体である(と自分は信じている)加害者が、オレは違う、やっていない、といっているときに、彼の言葉に従い、弁護人として無罪を主張するのか、或いは、己の確信に従い、弁護人は辞任するのか、そこには明確な規律はなく、弁護士によって考え方は全く違います。
因みに私の場合は、受任直後には無罪主張を要請した被疑者も、接見を繰り返し、否認することのメリットとデメリットを説明することにより、公判前に無罪主張を撤回するケースばかりでしたので、最終的に自分の確信と矛盾する訴訟遂行を迫られたことはありませんでしたし、辞任することもありませんでしたが、若い頃は、そうなったら辞任するしかなかろうと思っていました。
その考え方を根本から変えるきっかけとなったのが、和歌山カレー事件でした。一審で弁護を担当した弁護士についてのコメントをテレビで観たのですが、コメンテーターは、「有罪だとわかりきっている人の弁護をし、無罪主張をする弁護士の倫理観はどうなっているのか、理解できない。」と喋っていました。それを聞いて、強烈な違和感を覚えました。その違和感はどこから来たのか、暫く考えました。そして思い至ったのは、「有罪だと分かりきっている」と決めつけることの恐ろしさでした。
自分の家族、例えば息子が疑われたことを考えると身近に感じることができるかもしれません。総ての状況証拠が、犯人は自分の息子であることを示している、だが家族は皆、その息子がそんなことができる人間でないことは知っている、確かなアリバイはないが、犯行時間に彼が何をしていたのか、その説明には、これまでの彼の生活習慣からして十分に納得できる。ただ、そんなことは捜査官は全く理解していないし、理解しようともしない。そして息子が犯人であると決めつけている。そうなったときに「有罪だと分かりきっている」という理由だけで息子が有罪にされることの恐怖に考えが至ったとき、弁護人としての役割は自ずから明らかになりました。
それは、裁判所に対して、「この証拠関係だけでこの被告人を有罪として良いのか」という問題提起を行い、考えさせることです。例えばこのレベルの状況証拠だけで有罪が認定されるとすると、その効果は当該被告人に留まらず、それが刑事裁判のデフォルトになってしまう、それを許容して良いのか、そのことを裁判所に問いかかける、ということです。刑事法廷でその役割を担えるのは弁護人しかいません。そしてその役割は、極端に言えば、その被告人が実際に罪を犯していようがいまいが、弁護人である私が、彼が罪を犯したと思っていようがいまいが、その点は何等関わりません。この被告人は、この証拠関係で有罪にされる可能性がある、それは許容されて良いのか、という疑問があるとすれば、仮に個人的に有罪を確信していたとしても、その確信が無罪判決を得るための弁護活動を阻害することがあってはならないということです。
つまり、推定無罪が刑事裁判の大原則であるとすれば、推定無罪原則を貫徹させることが我々弁護士の役割である、その点が、そのとき改めて(というより初めて)私の腑に落ちたということになります。こと刑事弁護について言えば、私にとっての「正義」は推定無罪原則を守ることにある、ということになるように思います。
因みに「推定無罪」原則とは、冤罪の防止が基本的人権の擁護に直結するという憲法上の要請であり、その根底には、冤罪を防止するために結果的に10人の罪を犯した人間が無罪になったとしても、冤罪を容認するよりも法の信頼を高め、結果的には社会の安定に資するという考え方です。今の日本では、この推定無罪原則が有名無実化していると言われます。その原因は、日本の刑事司法の特殊性もありますが、より根源的には人間の生の感情に反するからだと思っています。テレビのワイドショーの刑事事件の報道を観れば明らかなとおり、あいつは悪人だと決めつけ、それを攻撃することは人間の本能に根ざしており、安易です。推定無罪原則はそういう人間の本能(或いはむき出しの感情)に反するものであるからこそ、積極的に擁護しようという強い意志が必要なのだと思っています。
私はその後も、そのようなギリギリの決断を迫られる刑事事件を請けたことはありませんが、仮に今後そのような案件が来たとしたら、どんなに世間から叩かれようと、自分の信念を貫きたいとは思っています。もうこの年齢なので、そのような案件が来ることはないとは思いますが。
因みに、これまでのところを前提として最初の命題に戻ると、麻原彰晃の弁護をすることは正義に反するとの結論になります。証拠上、彼が無罪になる余地はなかったからです。
更に因みに、私がこれまで刑事事件を扱った中で一番嬉しかったのは、執行猶予を勝ち取った国選弁護事件で、判決言渡の際に裁判官が被告人に対して「この件は、本当は実刑相当なのだ。ただ、国選弁護人が本当に一所懸命にやってくれた。君はそのおかげで執行猶予となったのだ。これからも弁護人に感謝して暮らしなさい。」と説示したときでした。
2022/9/1