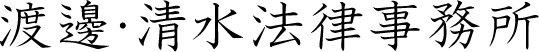第22回 弁護士の仕事はカッコいいのか(その2) - 契約書作成編
今回は、一年以上前に書いた証人尋問の話に続いて、弁護士の仕事の話の二回目です。今回は契約書作成編です。私は一応企業法務が専門ですので、依頼者から契約書の作成を依頼されることも多く、世の中に存在する範疇の契約書は、ほぼ作ってきたと思います。弁護士にとって、契約書を作る、或いは契約書をレビューするとはどんな仕事なのか、ご紹介したいと思います。
1. 契約書は何のためにあるのか
そもそも契約書は何のために存在するのでしょうか。
皆さん、この問いに対する答えはそれぞれお持ちだと思いますが、日本人同士の契約書と、外国人が当事者になっている契約書(あるいは海外の会社同士の契約書)の違いを先にお話しすると話が分かりやすくなるかもしれません。
日本人同士の契約書には、その最後に、「本契約書に定めのない事項については、信義誠実の原則に則り、当事者間で協議するものとする」とか「当事者間で紛争が発生した場合には、信義誠実の原則に則り解決するものとする」などというような条項が入るのが一般的です。極論を申し上げると、本質的に紛争を嫌う伝統的な日本人同士の契約書は、この一文、つまり「当事者間で信義誠実の原則に則って協議する」という条項だけあれば事足りてきたといっても過言ではありません。ところが、外国人や海外企業との契約にはこのような条項が入ることはなく、逆に契約書自体、とにかく長くなるのが普通です。
どういうことでしょうか。ご説明します。
外国人または海外企業が当事者の契約書はとにかく長い。なぜ海外の契約書は長くなってしまうのでしょうか。それは、海外の契約書は、契約締結後、実際に取引関係に入った後に当事者間で必然的に起き得る事態のみならず、発生するかもしれないトラブルや揉め事を想定しうる限りシミュレートした上で、その総ての筋道と解決方法を予め合意して、契約書に落とし込むからです。
つまり、海外の契約は、当事者が契約で規律しようとする取引関係に入った場合に想定される事態を総て想定し、その総ての事態に対する解決方法を契約書中に規定することが目的の一つであり、そのために契約書が長くなってしまうのです。
私はこれを、「行為規範」としての契約書の機能と呼んでいます。つまり、契約書は、当事者が取引関係に入ったのち、例えば「今日までに何をすればよかったんだっけ」という疑問が生じたときに、契約書を観ればその答えが明確に書いてある、という機能を持っていなければならないということです。
例えば、お金の貸し借りの契約書(「金銭消費貸借契約書」といいます)であれば、通常は、貸し借りの対象となった金額や割賦金の支払期日が契約書に記載されています。ですから、「えっと、次の割賦金の支払期日はいつだっけ?」という疑問が生じたときには、契約書を読めばそれが書いてある、それが契約書の最も重要な機能の一つです。これは最も簡単な例ですが、より複雑な行為が要求される取引関係であっても、契約書を参照すれば、当事者それぞれが行うべき行為が総て明確に記載してある、それが契約書に求められる「行為規範機能」というわけです。
言葉を変えると、契約書とは、当事者が行うべき行為、当事者間に発生する可能性のある事態が、総て一連のストーリーとして記載されている文書であることが求められる、ということです。
契約書にこのような行為規範機能を持たせるため、海外企業との契約交渉では、取引関係が発生した後に当事者間で起こり得る事態が総てテーブルの上に出され、その解決方法が議論されるのが通常です。その過程で、取引条件の詳細や当事者それぞれの義務の内容、義務履行のステップなどが議論されることになります。またそれに伴って、当事者間の取引関係が順調に進展している場合のみならず、一方当事者が契約書に規定されている行為を行わなかった場合など、何らかの不履行が発生した場合について、どのように解決を図るか、その方法も併せて議論されます。それが契約交渉なのです。
これに対し、日本人同士、或いは日本企業同士の伝統的かつ典型的な契約交渉では、相手方との間でどのようなトラブルが発生しうるか、どのような紛争が生じるか、などということを契約交渉の場でテーブルに出して喧々諤々の議論をするなどということは、基本的にはご法度です(ご法度でした、というべきかもしれません)。その文脈で、契約締結後に生じうる事態を想定してその解決手段を探るということ自体も、相手方と利害関係が衝突し得る事態、或いはそこまでいかなくとも、一定の緊張関係が生じ得る事態を敢えてテーブルの上に出す、ということに繋がるので、基本的には歓迎されません。これから仲良くなって契約を結びましょう、ということとなった相手方との関係が、契約締結後にギクシャクする場面や、相手方が契約上の義務を履行することを躊躇する場面などを想定すること自体不謹慎であり、失礼である、というのが伝統的な日本人のメンタリティであり、ぼくが先ほど、「伝統的な日本人同士の契約書は、『当事者間で信義誠実の原則に則って協議する』という条項だけあれば事足りる」と申し上げたのはそういうことです。
但し、日本企業、いや、端的に言えば日本人のメンタリティも、私が弁護士になった頃(そろそろ40年前になります)とはずいぶんと変わってきたように感じます。日本企業同士の契約書も随分と長くなりましたし、基本的には英文契約と同様、行為規範としての契約書機能を持つ契約書の割合も、圧倒的に増えてきたように思います。ただ、やはり日本人、「これ以上踏み込むと、相手方を怒らせるかも」というところまで契約交渉の場で踏み込み、取引条件を明確にしようとする企業の割合は、まだまだ少ないように思います。
いずれにしても、ここまでの話でお判りいただけたように、契約書が持たなければいけない機能の一つは、取引関係が開始された後の当事者間のストーリーが明確に記載されていること、すなわち行為規範としての機能です。
契約書のもう一つの機能は、「評価規範としての機能」です。
これはどういうことかというと、契約書中では、当事者のある行為がどのような効果を持つか(要するに行為者の行為がどのように評価されるか)が明確になっていなければいけない、ということです。先ほどの金銭消費貸借契約書を例にして申し上げれば、支払わなければいけない割賦金の支払いがない、という事態が想定されます(極めてわかりやすい例ですが)。この場合、相手方(お金を貸した当事者、つまり債権者ですね)に催告の義務を課すのか、その場合、催告期限をどうするのか、催告後なお債務者からの支払いがない場合、契約不履行を発生させるのか、そして債務不履行が発生した場合、どのようなペナルティが発生するのか(逆に言うと、債権者にどのような権利が付与されるのか)という一連の規定の終着点は、契約当事者のどのような行為がどのように評価されるのか、ということであり、契約書にはこのような機能も必要となるわけです。これが契約書のもう一つの機能であり、私はこれを「評価規範」としての契約書の機能と呼んでいます。
そして、このような契約書の評価規範としての機能を十全に発揮させるためには、先ほどの海外企業同士の契約交渉について申し上げれば、当事者間で発生する可能性のある不履行あるいは不作為をすべて交渉のテーブルに乗せ、その解決方法を協議して合意するということが必要となります。
伝統的な日本人(日本企業)同士の契約は、この点も交渉のテーブルに乗せることはありませんでした。日本企業のメンタリティも劇的に変化しており、ずいぶんと交渉スタイルは変わってきているとは思いますが、前述の通り、それでも海外企業の交渉スタンスのえげつなさに比べると、まだまだ開きはあるように思います。
2. 契約書を作成する上で重要なことは何か
我々弁護士が契約書を作成するときに意識することは何でしょうか。
重要なことはいくつかあります。例えば契約準拠法として指定された法律の条文や法原則に反しておらず、総ての条項が契約として完全にワークすること、各条項が論理的に破綻していないこと、当事者の意図と矛盾せず、その意図が総て盛り込まれていることなど、書き出せばきりがないくらい沢山あります。
しかし私が思うに、契約書で重要なことは、「わかりやすいこと」、これに尽きます。
先ほどご説明した契約書の二つの機能、それを十全に発揮させるためには、契約書を一読したときに、取引開始後のストーリーが明確になっており、当事者は何をしなければいけないのか、逆にどのような権利が与えられているのか、契約上の義務に違反した場合にどうなるのか、など、誰が読んでも解釈上の疑義なく、正確に理解することができるように、総ての条項が明確に、且つ端的に記載されていることが必要です。わかりやすい契約書とは、とりもなおさず論理的であり、且つ当事者の意図も明確になっています。そのような契約書であれば、締結後何年経っても、或いは契約作成者が総ていなくなっても、当事者間で疑義なく効力を継続させることも可能になりますし、契約当事者の意図が変化したのであれば、変更契約書の締結等でさらに継続的に効力を持たせ続けることもできます。
逆に契約書の内容が分かりにくい場合には、文言の解釈を巡って当事者間で見解の食い違いも生じ、それが紛争の火種ともなりかねません。何のために契約書を作ったのか、ということになってしまっては、弁護士がその作成に関与した意味は全くなくなってしまいます。
3. 契約書の勘所
先ほど、行為規範としての契約書の機能ということを書きました。契約書にはストーリーが記載されていなければいけないということを申し上げたわけですが、そうはいいつつ、契約書の中にも重要性の高い条項とそうでもない条項という区別は存在します。
重要性の高い条項とはどのような条項なのでしょうか。
重要な条項とは、まさしく、その条項がなければ契約書を締結する意味がない条項、更に言うと、取引開始後のストーリーの中核部分を構成する条項と言い換えてもよいかと思います。先ほどから何回か出てきた金銭消費貸借契約書を例にとると、幾らお金を貸しました、いついつまでに返します、という条項ですね。これについての記載がない金銭消費貸借契約書は、そもそも2020年改正以前の民法上の金銭消費貸借の要件(「要物性」といいます。詳細は割愛します。)が契約上明確にならないという決定的な欠点を抱えていたことになりますが、その点はともかく、少なくとも借りた金額の記載もなく、返済条件も当事者間の信義誠実な協議に任されているような契約書が、契約書としての意味を持たないことは明らかです。
金銭消費貸借契約書の例は極めてわかりやすい例ですが、それ以外の契約、ライセンス契約にしても、建物賃貸借契約にしても、株式譲渡契約にしても、仕組債発行契約のような、より複雑な契約にしても、その条項がなければ契約を締結する意味がない条項というのは、一本の契約書中に必ず複数存在します。我々が契約書を作成するときには、まずこのようなコアとなるべき条項を作成し、そのようなコア条項を機能させるためにそのほかの条項をどのように関連付けていくか、という思考方法で契約書全体を作っていきます。
逆に、当事者のストーリーとは無縁、或いはストーリーの中核を構成するわけではないが、契約書には定型的に入る条項も存在します。伝統的な日本企業間の契約書には、このような条項は全く入っていないか、入っていても極めて限られた条項しかなかったのですが、外国企業同士の契約書には非常に数多く存在しますし、日本企業間の契約書にも、このような条項が数多く含まれるようになってきました。
このような条項はボイラープレート条項と呼ばれます(ボイラーの表面に貼られているプレートのような、完全に定型的な文言の条項という意味です)。このようなボイラープレート条項は、ともすればネットに転がっている定型文言をそのまま丸写しで作成しがちなのですが、もともと英米法を起源とする条項が多いため、日本法の下では無駄であったり、機能しなかったりするものもありますし、当事者間の利益状況を徹底的にシミュレートしてみると、実は非常に奥深く、簡単に考えると思わぬ落とし穴があることに気づく条項もあります。
たとえば、ともすれば簡単に考えてしまいがちな準拠法や裁判管轄などの条項も、よく考えていくと、当事者の義務の内容やその履行の方法によって非常に複雑な検討が要求されるのですが、このコラムは法律上の論点の解説を目的とするものではありませんので、これ以上の説明は割愛します。
今回は弁護士がどのような観点で契約書を作っているのかというごく概括的なお話でした。ご興味を持って読んで頂けたでしょうか。残念なことに、これを読まれて、「弁護士の仕事ってカッコいい」と思われた方はおられないでしょうが。
9/9/25