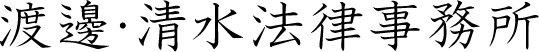第21回 良い弁護士の見分け方(その2)- 弁護士は評論家ではない
良い弁護士の見分け方の第一回として、訴訟に勝つ弁護士が良い弁護士とは限らない、というお話をしました。そうしたところ、かつての依頼者であったある方から、自分は弁護士を選ぶときに、ファイティング・スピリットのない弁護士と、データの読み方の甘い弁護士は選ばないようにしていた、というコメントを頂きました。なるほど、と思いました。
二回目の今回は、その方のコメントにヒントを得て、弁護士は何のために仕事をしているのか、という点に関わるテーマで書いてみようと思います。
このコラムの第2回に、「クライアントために最善を尽くす」ことについて書きました。私が弁護士になって以後20年間所属した森綜合法律事務所のポリシーであった「Best for Client」ということについてのお話でした。そこで書かせて頂いたのは、弁護士とはそもそも依頼者の利益の実現のために最善を尽くす職業であるということでした。今回は、この「依頼者のために最善を尽くす」ことは、実はかなりハードルが高い、というのがテーマです。
私たち弁護士は、依頼者の利益を実現することがその仕事の目的です。そのために依頼者の話を聞き、法律上可能な利益実現手段の選択肢を考え、選択肢それぞれについて論理構成を検討し、依頼者から収集した事実を当て嵌めて、どの手段を選択すれば最も効果的かつ効率的に目的を達成できるかを考えていきます。その結果、依頼者の意向が完全に実現できればメデタシメデタシなのですが、いつもそのような結果が実現できるとは限りません。むしろ残念ながら、そのような場合は必ずしも多くありません。多くの場合は、実際に戦闘が始まる前に、依頼者の意向に添えない部分があること、そしてその原因を依頼者に説明しなければならない必要性に迫られます。それは、戦闘開始前に、この戦いはどこに弱点があるのか、あるいはそもそも何故戦えないかを説明し、依頼者の理解を得なければならないということです。
このプロセスで依頼者の理解を得るために何が必要なのか、この点は「第3回 弁護士は依頼者に寄り添うべきか」でお話した通りなのですが、ここでも触れさせていただいた通り、実はこのプロセスが弁護士の能力の違いが最も端的に顕れるプロセスの一つなのです。ちなみに、この回、私は以下のように書いています。「与えられた情報、事実関係から、利害状況を端的に紐解き、その上で依頼者の利益を実現するためにはどのような事実が必要か、与えられる情報にどのような事実に関する情報が不足しているのか、どこで勝敗が決せられるのか、当方及び相手方にとって決定的に有利・不利な事実は何か、負けないためには何が犠牲になるのか等々を精緻に分析して、簡潔に分かりやすく説明する、それができなければ依頼者は絶対に納得してくれません。そして、このような説明は、案件全体を冷静かつ客観的に俯瞰し、精緻に分析してこそ初めて可能になるのであり、しかも、依頼者の希望が実現できないことを端的に伝える覚悟と強さを持たなければなりません。」まさしく、これができるかどうかが、弁護士として有能かどうかが最も問われる場面の一つだと言っても過言ではないのです。
そして、読者の方からの冒頭のコメントにある、「ファイティング・スピリットのない弁護士」と、「データの読み方の甘い弁護士」というのは、このプロセスに関連して、結果的に、目の肥えた依頼者から最も敬遠される弁護士の典型です。ただ我々は誰でも、ともすればこのような弁護士として見られてしまう可能性を持っています。換言すれば、この「ファイティング・スピリットのない弁護士」や「データの読み方の甘い弁護士」という評価を受けてしまう可能性は、我々弁護士にとって、最も陥りやすい危険な罠だと言っても過言ではありません。
では、なぜ弁護士は、「ファイティング・スピリットのない弁護士」や「データの読み方の甘い弁護士」という評価を受けてしまう危険性と隣り合わせなのでしょうか。
これは、私たち弁護士は「評論家」ではなく、「代理人」なのだということと深く関連しています。依頼者から「この弁護士はファイティング・スピリットがない」とか、「この弁護士はデータの読み方が甘い」と評価されてしまう弁護士は、依頼者にとって「代理人」ではなく、「単なる評論家」と評価されてしまったということなのです。
ご説明します。
依頼者は我々のところに、案件の客観的な評価を聞くために来られているわけではありません。あくまで、依頼者のために、依頼者を代理して、依頼者の立場で(いわば当事者として)戦うことを求めているわけです。他方我々は、案件の内容を精緻に分析して、依頼者の立場の弱い部分も含めて(むしろそれに主眼を置いて)、案件の全体像を簡潔に分かりやすく説明しなければなりません。そして「このような説明は、案件全体を冷静かつ客観的に俯瞰し、精緻に分析してこそ初めて可能になる」わけです。つまり弁護士は、「依頼者の立場で戦う」ことと、「案件の見立てを第三者の立場で客観的に説明する」ことという、本質的に相反する二つのことを同時に行わなければならないのです。
そして、「案件の見立てを第三者の立場で客観的に説明する」ときに、「依頼者の立場で戦う」ことを忘れてしまうと、依頼者の眼からすると「我々は弁護士の評論を聞きにここに来たわけではない」、或いは「これでは何のためにこの弁護士に相談しているのかわからない」ということになってしまうのです。
そしてこの「評論家のような弁護士」の端的な例が、「ファイティング・スピリットのない弁護士」と、「データの読み方の甘い弁護士」なのです。
「ファイティング・スピリットのない弁護士」とは要するに、最初から本気で戦う気がない弁護士のことです。検討を依頼された案件が難しそうだと感じると、依頼者の依頼に沿うことがいかに難しいかということだけを滔々と論じ、「そこを何とかして頂けませんか」と言われても「いやダメなものはダメですよ」と、半ば薄ら笑いさえ浮かべてシャットダウンする、そういう弁護士を想像してください。依頼者からすれば、難しい案件であることは自分たちも最初からわかっている、でも何とかして欲しいから法律事務所の門を叩いている、そうして頼っている我々に対して、知恵を絞ってできる限りの手を尽くすこともしないで、評論家風情で偉そうに講釈を垂れるような弁護士、そんな弁護士は要らない、ということになってしまうのです。
「データの読み方の甘い弁護士」、これも「評論家」の亜流です。こういう弁護士は、依頼者がまとめたデータの深いところを読み込もうともせず(或いは読み込む能力がなく)、一瞥した印象だけで自分の都合の良いように解釈してその案件の難易度を判断し、安直に結論を出してダメ出しをする、そういう弁護士です。そういう弁護士もまた、依頼者からすれば、本気で戦う気のない弁護士と映ってしまうわけです。
ちなみに、この「データの読み方の甘い弁護士」には、逆のパターンもあります。データを自分の都合の良いように解釈して、「これはイケますよ」と安直に結論を出してしまうというパターンです。こちらは評論家とは違うのですが、依頼者にとってみると、評論家風情の弁護士より危険です。評論家は自分たちのために戦ってくれないので、安易に案件に突っ込んでいくということはありませんが、こういう「イケイケ」型の弁護士に捕まってしまうと、案件が進むにつれ、より深刻な結果が招来される危険があるからです。いずれにしてもこういう弁護士も、本気で依頼者のために戦おうとは思っていない。基本的には、案件の表層だけ撫でて自分たちの仕事は終わりだと思っています。
実は、評論家だか何だかよくわからない弁護士というのは、結構世の中に沢山棲息しています。なぜかというと、評論家として原理原則を一般論として喋っている方が明らかに簡単だからです。
依頼者が案件を相談に来られた際に我々がまず行うことは、法理論或いは法原則と言われているものに則った一般論の解説です。「ご依頼の件には、A、B二つの解決方法があり得る、だが、選択肢Aはこれこれの要件が必要だし、選択肢Bにはこういう難点があるところ、ご相談の案件は、どちらの選択肢に関しても、要件を満たしていないと思われる」という風に。そして、この一般論を正確に説明することにも、それなりの能力と経験、そして準備が必要であり、それだけでも一応その対価を頂戴することもできます。それ自体弁護士としての専門知識の開陳だからです。
ですが、弁護士の本当の仕事はここからです。
どんな案件にも必ず弱点があるように、逆に必ず突破口もあります。その突破口を、依頼者と共に悩みながら、時間をかけてリサーチをし、必死に探していく、それは非常にしんどい作業です。しかし、それこそが代理人としての弁護士の仕事であり、実はそのプロセスこそが、「血沸き肉躍る」プロセスなのです。そしてそれを支えるのが、冒頭の「ファイティング・スピリット」なのだと私は思います。評論家で終わってしまう弁護士は、この、辛いが血沸き肉躍るプロセスを、意識的にか無意識にか避けてしまうのです。
かくいう私自身も、評論家にならないよう日々気を付けていますが、まだまだ研鑽と鍛錬の日々です。そもそも、そういうファイティング・スピリットをいつまで持ち続けられるか、それが目下の課題です。それがなくなったらとっとと引退します。
というわけで今回は、「評論家にならない弁護士」を選びましょう、というお話でした。ただ、その弁護士が評論家でないかどうかは、実際に仕事を依頼してみないとわかりません。その意味では、「評論家にならない弁護士の見分け方」をご指南申し上げることはできません。
申し訳ございません。
8/21/25