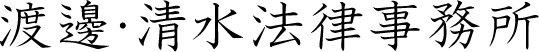第19回 エクイティ(Equity)って何?
しばらく更新をサボっていました。申し訳ありません。半年ぶりの更新です。
あるSNSに、トランプ大統領が打ち出した、アメリカの一部の法律事務所に対する報復を内容とする大統領令に関して、私がアメリカで研修させてもらった法律事務所のことを書きました。その大統領令というのは、例えば、かつての議会乱入事件等の捜査にかかわった弁護士をメンバーとする法律事務所に対し、連邦政府の建物への立入を禁止することや連邦政府の情報提供を制限することなどを内容とする完全な嫌がらせなのですが、これに対する対応が事務所ごとに異なっており、トランプに妥協して取引する事務所と徹底抗戦する事務所とで完全に分かれました。そして、私が研修したシカゴのJenner & Blockという法律事務所は、この大統領令に対し徹底抗戦し、先ごろ連邦地裁から大統領令が憲法違反であるとの判断を勝ち取りました。
私は何を隠そう(別に隠す必要もありませんが)、このJenner & Blockという事務所が大好きです。今回私がアップした記事をご覧になれば、私がどれだけこの事務所が好きかお分かりになると思うので、記事をそのまま(多少加筆して)ご紹介します。
「アメリカの法律事務所も様々だ。
ぼくは徹底抗戦している事務所の一つ、Jenner & Blockで、93年から95年までインターンをした、この事務所で働いた最初の日本人弁護士なのだが、彼らは当時既に全米トップランクの訴訟事務所としての名声をほしいままにしつつ、徹底的にリベラルでフェア、しかも好戦的(攻撃的ともいう)だった。当時ぼくのいた森綜合法律事務所といろいろな意味で非常に似通っていて、ぼくも一所懸命働いたし、事務所のチェアマンにもとても可愛がってもらった(註:このチェアマンというのが、「第14回 本物は普通で無駄がない」でご紹介した、私のアメリカの師匠です)。いまもなお、昔と全く同じように、筋を通すことを何より重んじる人たちが沢山いるというのは、卒業生の端くれとして非常に嬉しい。
他方、トランプと妥協した事務所のラインナップを観ると、これはこれで、なるほど、さもありなんという印象。この記事の言うように、だからといってクライアントが離れていくというようなことはないだろうが、組織の性格というのは数十年経っても基本変わらないのだな。非常に興味深い。」
まあとにかく、30年経っても、リベラルでフェアで、年齢性別関係なく正論を重んじ、逆に筋の通らないことには徹底的に嚙みつく人たちの集まりだったこの事務所のカルチャーが全く変わっていないことに物凄く感激したわけなのですが、その記事をSNSにアップしたときに、「IntegrityとEthicsはprofessionalの根幹ですよね。そこは妥協出来ないと思います。」という、現在NYにお住いの、企業内部監査の専門家の方からのコメントを頂戴しました。まさにその通りというコメントなのですが、ぼくはこのコメントに対し、「おっしゃる通りですね。ちなみに最近日本でも、ガバナンスの文脈で、EquityだのIntegrityだのという単語が飛び交うようになりましたが、その深遠な意味を理解している人がどれだけいるんだろうとは思います。」というコメントをお返ししました。
これはまさしく、最近、コンプライアンスやコーポレート・ガバナンス絡みの議論を耳にするたびに感じる違和感なのですが、私のこのコメントを読まれたかつてのクライアント(その方は、このコラムも欠かさず読んでくださっている方なのですが)の方から、Integrity、Ethicsと私の仕事との関係や、「企業のなんちゃってキャッチコピーとかの話」を読んでみたい、とのリクエストを頂戴しました。「企業のなんちゃってキャッチコピーとかの話」という表現は、まさしくその方の真骨頂という感じなのですが、私も基本全く同感です。
前置きが長くなりましたが、本日のテーマは、そういうわけで、チコちゃん風にいうと、「エクイティ(Equity)って何?」です。
その前提として、最近ガバナンスの文脈でIntegrityだのEquityだのを耳にすることが多くなった背景を少しご紹介します。コンプライアンス概念の変遷の話です。少々お付き合いください。
コンプライアンス(Compliance)概念が日本に導入された 1990年代、この言葉は「法令遵守」と訳され、企業が法令・規則等のルールを遵守して経営することであると解説されてきました(当時、自らこの言葉を「法令遵守」と訳して使っていた弁護士が、今頃になって「最初にこれが法令遵守と訳されたことが、日本企業がいまだに不祥事から足を洗えない根本原因だ」などと批判していますが、それはそれとして)。
しかしながらその後、コンプライアンス概念は時代とともに変遷し、今日コンプライアンスとは、企業統治を意味するガバナンス(Governance)を達成するための体制を構築する目的として位置づけられています。そして、ガバナンスの目的が、単なる法令遵守に留まらず、それを前提とした上での健全な企業風土、企業倫理等の確立にあると認識されるように変化するに伴い、ガバナンスの目的たるコンプライアンス概念についても、健全な企業風土、企業倫理等をも包含するより広い概念として認識すべきであるという議論が出てくるようになりました。
更に、このコンプライアンス概念をインテグリティ(Integrity)概念に対応させ、上から何らかの遵守を強要されるコンプライアンス概念ではなく、企業の構成員一人一人が主体的に企業風土を変えていく概念として企業に根付かせることが必要であるとの論調も見られるようになっています。
また、エクイティ(Equity)は、Integrityと同様に、企業の構成員一人一人が主体的に企業風土を変えていくという意味で、コンプライアンス概念を構成するものの一つとして位置づけられており、社員に対するアンコンシャス・バイアス(Unconscious Bias「無意識のバイアス」と訳されます。本人も気づかず、無意識のうちに、職場の人間を差別してしまったり、傷つけてしまったりすることを言います)根絶の文脈として、日本企業の流行語の一つとなっているDE&I(Diversity Equity and Inclusion)「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」(多様性、公平性、包括性)の構成要素として使われています。これは、社員がその職場で働くについての心理的安定性を確保するために、多様で公平で、誰をも受け入れる職場を作ろう、というものです(ちなみに、EquityにしてもIntegrityにしても、変容したコンプライアンス概念そのものは、当然海外が発祥ですが、日本企業で導入の動きが広がっているのは、いかにも日本的な話で、経産省がこれらわけのわからない英語をそのまま使ってガイドラインを作っているからです。)。
ここまでが前振りです。お分かりになりましたか?何を言っているのかよく分かりませんよね。実は私にもよく分かりません。なぜ分からないかというと、このコンプライアンス概念の変化の中核として機能しているIntegrityだのEquityだのという英単語の意味が我々には全く馴染みがないからです。もう既に目が回りそうなのですが、気を取り直して、Equity、Integrityの意味を少々解説します。
まずはEquityから。なぜEquityからかというと、これは法律用語なので、私も少々解説できるからです。
Equityは英米法の概念です、読者の皆様の多くがご存じのように、英米法の体系は、ヨーロッパ大陸法(代表的なものがドイツ法やフランス法などで、日本法はこの大陸法を起源としています)とは異なり、成文法体系ではありません。つまり、英米法には、日本でいうところの民法や刑法や会社法といった、法典の形で文章化、体系化された法律は(伝統的には)存在せず、基本は慣習・判例の集積が法律として機能しています。伝統的には、と言ったのは、今日においては、英米法系の国でも重要な法律は成文法の形でまとめておかないと法が社会規範として機能しない事態が多発するため、成文法(いわゆる法律)も数多く存在するからです。その意味では、判例法の国と成文法の国の本質的な違いは小さくなっているといえるでしょう(例えば、アメリカの会社法のモデルとして有名なデラウエア州会社法なども立派な成文法です)。
しかし、慣習法・判例法である英米法と、成文法である大陸法の違いが小さくなったとは言いながら、厳然として存在する違いのひとつは、英米法にはEquityが残っている、という点です。この場合のEquityは、衡平法と訳されます。その起源は、イギリスの慣習法(コモンローと言われます)では救済できない権利関係を、大法官(Load Chancellor)、日本的に言うと最高裁長官が直接救済したことに由来しています。つまり既存の法体系では論理的には救済できない場合、論理的な解決方法に依拠すると当事者間の公平が害されると大法官が判断するときには、当事者の衡平の観点から特に救済が与えられることがあり、その根拠がEquity(衡平法)です。そして、そのようなEquity上の救済を与える裁判所がChancery Court(衡平裁判所)と言われます。因みに、先ほどデラウエア州会社法のことを書きましたが、デラウエア州には、今日でも、会社法上直接の規定のない救済を与える裁判所として、衡平裁判所が存在します。この衡平裁判所からは、企業買収に直面した場合の取締役の義務や経営判断の原則などに関する重要判例が出されています。
また、英米の裁判では、Chancery Courtでなくとも、この衡平法に基づく救済が行われることはしばしばあります。例えば法原則を機械的に適用していくと当事者間の衡平を損なうと判断されるときなどに、裁判所がEquityとしてのFiduciary Dutyなどを持ち出して、当事者間での衡平な解決を図る、というようなことが行われます。皆様もすでにお気づきのように、これは日本法上の概念である、信義誠実の原則や、公の秩序などの一般原則を裁判所が適用することにも通じるものがあるといえるでしょう。
というわけで、Equityというのは、もともと、非常に歴史の古い、しかも非常に抽象的かつ曖昧な、だからこそ、非常に難しい法律概念であり、こういう言い方をすると何を偉そうに、と思われるかもしれませんが、英米法概念に少しでも接したことのある人間でなければ、そもそも、何を言っているのかわからないはずの単語なのです。例えば、「公平性」は「Equality」でもよいはずです。DE&Iが、なぜ「Equality」ではなく、「Equity」を使うのか。それを理解しようとすれば、Equityの起源とその発展の歴史を勉強しなければならないでしょう。EqualityとEquityの違いも意識せず、流行言葉としてのDE&Iを「なんちゃってキャッチコピー」として使うのは簡単ですが、おそらくそのようにして使われる言葉には、言霊は抜けてしまっているのはないかと思わずにはいられません。
これに対し、Integrityは法律用語ではありません。衡平法上の救済の中には、Integrityを理由に救済を行った事例は存在するかもしれませんが、救済の根拠としてのEquityと同じ文脈で、法律用語としてIntegrityが使われることはないように思います。また、私のような英語の素養の乏しい者にとって、Integrityのネイティブにとってのニュアンスなどわかるはずもありません。直訳すれば、「高潔・誠実さ、品位」などということになるのでしょうが、正直、「企業のガバナンスにIntegrityが必要」と言われても、何を言っているのか全く分からない、というのが正直なところです。
企業の経営指針にやたら英語が使われるようになったのは、2015年の金融庁と東京証券取引所によるコーポレート・ガバナンス・コードの制定のころからだったように思います。そもそもコーポレート・ガバナンス・コードそのものが、OECDのコーポレート・ガバナンス原則(Principles of Corporate Governance)の直訳だった訳ですので、それも無理からぬところなのですが、「Comply or Explain」だの、何を言っているんだと思ったものです(今でも思っています)。きちんと日本語にしろよ、と。EquityにしてもIntegrityにしても同様で、日本の会社の行動指針にするのであれば、日本で根付く日本語に置き換えてほしいと思います。かつて明治の日本人がそうしてきたように。余談でした。ついでにEthicsについて申し上げておきます。
Ethicsは比較的わかりやすい言葉で、これはまさに倫理です。我々弁護士にとっては、Ethicsこそがその職業的存在の根源というほど重要な概念です。近年の弁護士の不祥事の多さは、まさしく目を覆うばかりですが、これはもともと、弁護士という仕事が常に誘惑と隣り合わせであること原因があります。我々がEthics、すなわち弁護士としての職業上の倫理を捨ててしまったら、あとは落ちるところまで落ちるだけです。
最後に、本論とは無関係ですが、コンプライアンス概念の変容が弁護士の業務にどのような影響を与えるかという点について若干コメントしておきます。
コンプライアンス概念がどのように変容し、拡大したとしても、その根本に法令を遵守するという概念が存在することは疑いようもないと思っています。健全な企業風土とは、適法経営の上にこそ構築されるものだからです。但し、この「適法経営」概念そのものを観ても、コンプライアンス概念の変化が、その根本にある法令遵守の在り様にも影響を及ぼしていることは注目に値します。法令遵守の在り様の変化とは、法律を遵守する必要がなくなったということを意味しないのは当然のことです。そうではなくて、その目的、着地点の変化に合わせて、遵守すべき法律の外延が拡がった(ミニマルな法律のみならず、より積極的に、或いは自主的に遵守すべき法律が加わる)ということであり、また、法令遵守のために取引の相手方等のステークホルダーにも法令遵守を要請し、より積極的に訴訟等のアクションを提起するということもあり得るということです。
そして、このような、コンプライアンス概念の変化に対応した企業の法令遵守の在り方、目的達成のために採るべき手段の選択などに関して企業の求めるアドバイスを行うためには、そもそも法律専門家として十分な知見と経験を持っていることが最低限必要ですが、更にそれ加え、企業の経営、業務執行の在り方について深く理解することが必要であることは言うまでもありません。当該企業の健全な企業風土を維持発展させる基本に法令遵守があることを踏まえた上で、企業の法令遵守の在り方を検討することもまた必要不可欠となっていると思っております。
以上、長くなってしまいましたが、「なんちゃってキャッチコピー」についての話題でした。
7/7/25