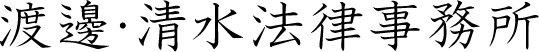第16回 弁護士の仕事はカッコいいのか(その1)- 証人尋問編
これから何回か、弁護士はどんな仕事をしているのかについて書いていきたいと思います。「弁護士の仕事はカッコいいのか」というタイトルではありますが、いかにカッコいい仕事をしているのかについて書きたいのではなく、その仕事の中身について、いくらかでもご理解頂きたいというのが本旨です。
一回目は法廷での弁護士の仕事の一つ、証人尋問についてです。
かつて私が所属していた法律事務所では、裁判所での証人尋問期日が入ると、その弁護士の担当秘書や事務局スタッフに法廷を傍聴してボスの尋問を見てもらうということが時々ありました。大抵の弁護士は、性格も生活態度もグダグダなので、秘書に弁護士の仕事の本籍地である法廷での仕事振りを見てもらい、本当は仕事のできる人なのね、と思ってもらう、という目的がありました。いつも家でゴロゴロしているお父さんが職場では凄い、というところを見てもらうために子供を職場に招待する、というのと同じようなものです。ただ、職場参観の結果が却って逆効果になることもあるように、法廷傍聴もその結果はまさしく悲喜交々で、「あんなに凄い尋問をする先生だったなんて・・・・」と感動して帰ってくるスタッフもいれば、法廷傍聴の結果、前より秘書の風当たりが辛くなったという気の毒な弁護士もいました。
余談ですが、自分の婚約者が「キミの証人尋問が見たい」というので、尋問を傍聴してもらった女性弁護士がいたのですが、相手方に対する反対尋問があまりに厳しかったため、その後、「あんなに恐ろしい人だったんだね、キミは」と本気で怖がられてしまい、関係が壊れかけてしまったので、どうして自分がそういう反対尋問をしたのか、弁護士がどのように証人尋問を準備するかについて、その詳細を説明し、漸くわかってもらった、という事件もありました。ちなみに、その説明の内容が今日の本題ということになります。
新人を事務所にリクルートするために司法修習生と採用面接をすると、「テレビドラマの弁護士がカッコよかったので弁護士を志しました」という人たちが一定の割合存在します。弁護士の仕事全般がカッコイイかどうかについて書き始めると、恐らく途轍もなく長くなるのでやめますが、少なくともドラマの中で弁護士が最もカッコよく見えるのは法廷での証人尋問でしょうね(ですから秘書に尋問を傍聴してもらうわけです)。ただ、弁護士の証人尋問がカッコイイかどうかについてどんなに語っても、「結局それって弁護士次第だろ、SUITSのHarvey Specterみたいに弁護士がカッコよければカッコよくなるさ」と言われて終了なので、そんなことで時間は費やしません。代わりに今回は、証人尋問を成功させるために弁護士はどんなことをするのか、ご紹介しましょう。
私が若かったころ、年配の弁護士には、証人尋問は経験が勝負、準備などは要らないと言っていた人たちが結構多かったように思います(今でも多いのかもしれません)。また、これも今でも多いのかもしれませんが、特に相手方の当事者や証人を反対尋問する際に、必要以上に威圧的になって証人を委縮させ、或いはわざと怒らせて冷静さを失わせて有利な証言を引き出そうとする弁護士も何度も眼にしてきました。勿論、場数を踏むことによる経験が助けになることは否定しません。また、証人を威嚇したり怒らせたりすることにより、有利な証言を引き出せることもあるかもしれません。しかし、経験やそのような戦術により常に尋問が成功するものではないことは明らかです。
証人尋問を成功させる唯一の秘訣は、準備です。それ以外にはありません。
どのような準備をするのか、その詳細を具体例で詳らかにすることはできませんが、主尋問については、証人が記憶している事実を無理なく自然に、しかも過不足なく法廷に顕出できるよう、質問の内容、順番を、証人の記憶と擦り合わせながら、何度もブラッシュアップします。よく、「弁護士は証人をトレーニングして、弁護士が構成した主張に沿って事実を変える(極端なことをいうと、捏造する)のではないか、そしてそれに合わせて証人にも虚偽の事実を言わせることもあるのではないか」というような質問を受けることがありますが、それは全く違います。訴訟当事者にしても証人にしても、自分の記憶にないこと、或いは自分の記憶と違うことを、第三者から押し付けられて法廷で話すことはできません。規範的にできないという以前に、物理的にできないのです。人間はそれほど器用ではないからです。仮にそのような証言を押し付けられたとしても、人は記憶と違うことを話そうとすると必ずしどろもどろになりますし、そこを何とか乗り切ったとしても、必ず論理的に破綻します。裁判官もそのあたりは実によく観ているのです。我々弁護士にとって最も大切なことは、裁判所から「あの弁護士は虚偽の事実を主張しない、当事者にも虚偽を押し付けない」、逆に言うと「あの弁護士(或いは「あの事務所」)の主張する事実であれば、それは真実であるという前提で検討してよい」という信頼を得ることであり、そのような信頼を得ることが、依頼者の利益に直結するのです。無理をしてもそれは結局依頼者の利益にならないということです。
また反対尋問については、相手方の当事者または証人が依って立つであろうストーリーを予想し、その矛盾点を総て洗い出すことが準備の出発点です。そうして洗い出された矛盾点をいかに裁判所に印象付けられるか、それが反対尋問の目的となります。どのような質問をしたら相手方はどのように答えるか、考えられる総ての回答を想定し、更にそれに対する次の質問も想定し、場合分けしてフローチャートにして、Aと答えたら次はこの質問、Bと答えたらこの質問、という風に質問を組み立てていきます。
このような準備をして尋問を行えば、主尋問にも反対尋問にも経験など全く不要です。主尋問については、証人の証言は総て自然に流れていきますし、反対尋問についても、証人がどのような証言をしたとしてもその証言は全て想定済みであり、そのヴァリエーションに応じて次の質問も考えてあります。フローチャートに従って、淡々と尋問していけば、相手はこちらの用意した落とし穴に自然に落ちてくれます。威嚇して委縮させる必要も、怒らせて冷静さを失わせる必要もありません。
勿論、このような準備には膨大な時間を要します。複数の案件で証人尋問が一週間に複数予定されたりすると、基本寝ている時間は無くなります。
冒頭にご紹介した、婚約者を怖がらせてしまった女性弁護士も、このような事前準備を行い、予め想定していた質問を淡々と重ねていった結果、相手方証人がこちらが用意していた落とし穴にいつの間にか嵌り、後戻りできなくなって慌てふためき、最後は救いを求めてきた(先程の証言は間違いだったので訂正させてくれ、と泣きついてきた)。にもかかわらず、彼女がにこやかにそれを拒否し、証人がパニックになるのを涼しげな笑顔で眺めていた、というだけのことです。
ついでに申し上げると、反対尋問で絶対に行ってはいけないのが、相手方証人がこちらの望む証言をしなかったときに、「今・・・・・と仰いましたが、それは本当ですか」だの「本当は・・・・なのではないですか」だのと質問することです。そのように質問したとしても、証人は「もちろん私の申し上げたことが本当のことです」と答えるに決まっています。要するにこのような質問は、結局相手方の証言を固めるだけの効果しかないのです。反対尋問は、相手方の主張する事実関係の矛盾点をつくことに目的があり、それで十分なのであって、当方の主張する事実関係と相手方の主張する事実関係の違いを証人に認めさせる必要など全くありませんし、従ってその点を問い質す必要も全くないのです。上記の例でいえば、証人が認識している事実関係がこちらの主張と異なるのであれば、その証人の認識に基づく帰結を淡々と積み重ねさせていき、それら事実関係が内在している矛盾を証言から明らかにさせればよいのであって、「いやいや、あなたの言っていることは嘘でしょう」などと詰問する必要など全くありませんし、無意味です。証人自身に反対尋問の理想は、証人が全く気付かないまま、その主張する事実関係の矛盾がいつの間にか鮮明になっていることであって、その意味で、証人がその証言の出来に満足している反対尋問が最も成功した反対尋問になっていることもあるほどです。
昔、反対尋問で証人に好きにベラベラ喋らせ、最後に「なるほど、よくわかりました。しかし、そのご証言のとおりだとしますと、あなたの行為は証券取引法(今は金融商品取引法ですが)違反ですね」という質問で尋問を締めくくったことがあります。証人はぼくの最後の質問で初めてそのことに気づき、顔面蒼白になって押し黙るしかありませんでした、総て後の祭りです。私は「では終わります」と言って、尋問を終了しました。依頼者からは、「いやー、恐ろしい。まさしく寸止めの美学ですね」と感嘆されました。これも総て準備の賜物です。徹底した合議をしてくれたチームメンバーに感謝しました。
このような反対尋問ができた時には、弁護士もカッコよく見えるのでしょうが、残念ながらそのような機会は滅多にありません。
ついでに蛇足ですが、この「カッコイイ弁護士」に関連してアメリカのTrial Lawyerの話をひとつ。アメリカの裁判は、民亊でも刑事でも陪審裁判が原則です。刑事の場合は、有罪か無罪かの評決を行い、民亊の場合であれば、被告に課せられる損害賠償額についても陪審員が決定します。このため、Trial Lawyer(法廷弁護士)は、依頼者を勝訴に導くためには法律の素人である陪審員を説得しなくてはならず、事案の概要や難解な法律概念を、平易な言葉で誰にでもわかるように、しかも端的に説明する能力が求められます。このコラムの第14回でご紹介した、ぼくがシカゴの法律事務所で師事した事務所のチェアマンは、極めて優秀な法廷弁護士でしたが、彼はまさにこの点でも突出した能力を持っていました。同じくそこでご紹介した、ぼくの日本の師匠のいう「難解なことを誰にでもわかるように簡単に説明できる一握りの弁護士」だったわけです。
ただ、繰り返しますが、陪審員は法律の素人ですので、容姿、服装等、弁護士の第一印象に極めて左右されやすいともいわれます。そこでアメリカの法律事務所の中には、専門のコンサルに依頼して、選任された陪審員全員について、その性別、年齢、職業、居住地区、宗教、家族構成、学歴などあらゆる情報を収集し、彼らと同じバックグラウンドの人間を陪審員と同人数を集めて傍聴席に座らせ、法廷弁護士の訴訟活動に対してどのような印象を持ったかを毎日レポートさせ、事務所にフィードバックして翌日からの訴訟活動の参考にする、という戦術を採る事務所もあります。そのフィードバック項目の中には、弁護士の容姿はどうだったか、服装は許容できたか、ネクタイやチーフの色や柄は派手過ぎなかったか、等々の項目も含まれているそうです。私が日本に帰ってこようと思った理由の一つは、とてもじゃないが、自分はこんなところで評価してもらえる外見ではない、ということでした。
ついでに更に蛇足ですが、テレビドラマでの証人尋問は、大抵現実と大きくかけ離れていますが、これまで私が見たリーガルドラマの中で、証人尋問の描写が非常にリアルだったドラマが二つあります。一つはちょっと前の、唐沢寿明と江口洋介主演の「白い巨塔」、このドラマでは、唐沢寿明と江口洋介が対質尋問を受けるシーンがあるのですが、この法廷描写は秀逸でした。もう一つは今の朝ドラの「寅に翼」、ここでは主人公の寅子の父親が関与を疑われた疑獄事件の法廷風景が描かれたのですが、小林薫が演じる被告人弁護人の主任検察官に対する尋問の描写が、法廷の緊張感(いわゆる「ヒリヒリした感じ」)を見事に醸し出していて、非常に印象的でした。
今回は余談が多かったですね。次回は弁護士の仕事について続きを書いてみたいと思います。
2024/08/22