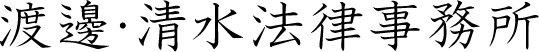第15回 社外取締役をおくことにどんな意味があるのか
このコラムも15回目になりました。
これまでここでは、具体的な業務上のトピックスを取り上げることはしませんでしたが、今回は、最近仕事で感じていることを書くことにしました。
社外取締役の在り様についてです。
相当ニッチな分野の話なので、興味のない方は無視してください。
ここ20年以上、いろいろな会社で社外役員として取締役会に出席して、社外取締役の皆様と関わり、彼らの取締役会その他の機関での発言を聞いてきましたが、社外取締役の会社にとっての役割について、年々モヤモヤが募ってきました。そしてそのモヤモヤは、年を追うにつれて増すばかりでした。
最近日経新聞に、藤田勉一橋大学大学院経営管理研究科客員教授による、「社長選びは間違いだらけ? 日本の『米国流ガバナンス』」という記事が掲載されていました。その記事を読んで、ぼくが感じていたモヤモヤがある程度整理されました。それを端的に言えば、「社外取締役が増えれば会社のガバナンスに資する」というテーゼは、全く検証されていない単なる妄想ではないのか、ということです。
なぜこう思うに至ったか、その理由は大きく二つあります。
一つは、日本の社外取締役は、会社法が期待しているように、独立役員として忌憚なく経営陣にものを言っているのか、という疑問です。
もともと、社外取締役は、英米系企業、特に米国企業において導入され、発展してきました。その根底には、株式会社にとっての最大の利害関係者(いわゆる「ステークホルダー」)である株主に還元すべき企業価値を最大にすることが経営者の使命であり、かつ、この企業使命は、投資家以外の利害関係者と密接な関係を有する取締役のみで構成される経営陣では達成できず、会社を取り巻く利害関係者のいずれからも独立した人間が取締役会の構成員になっている必要があるという考え方が存在しています。特に2001年のエンロン事件以降、その傾向が顕著になり、証券取引所規則の改正等を通じて、社外取締役の独立性要件が厳格化されるなどの改革が行われてきました。
我が国において現在の社外取締役導入の契機となったコーポレートガバナンス・コードは、まさしくこの潮流を汲むものです。同コードは、2015年のG20において採択されたOECD(「経済協力開発機構」)のコーポレートガバナンス・コードをそのまま直訳したものですが、その根底にあるのは、OECDコーポレートガバナンス・コードが、「G20が優先事項として掲げる、企業の資本市場を通じた資金調達の促進をサポートするという点において重要な貢献をする」との考え方です。つまり、会社が投資家である株主に対する説明責任を果たし、その資金調達を促進させることが企業には求められており、そのためには企業価値を向上させることが必要不可欠である、そして、この企業価値の向上は、企業がそのガバナンスを充実させなければ達成できない、という考え方が根底にあります。
社外取締役の設置は、まさしくその一環として位置づけられるのです。
要するに、社外取締役は、「会社との利害関係を離れ、独立した客観的立場で、忌憚のない意見を開陳し」もって「企業価値の向上」に資することが期待されているのです。ですから、独立の立場で客観的に行動することが求められる社外取締役には、本コラムの「第13回 胆力とは」でお書きしたように、まさしく弁護士同様、胆力が求められる役職といえるのです。
ところが、ここ20年ほど、数多くの社外役員の方々とお付き合いさせて頂いてきた経験で申し上げると、時に会社経営陣、或いは大株主の意向に反しても、どんな状況でも、誰に対しても、忌憚なく正鵠を射たことを端的に述べることができる社外取締役には、実はあまりお目にかかったことがありません。日本には社外役員になるべき人材が少ないということが時に議論されますが、このような胆力のある社外役員が果たしてどれだけいるのか、非常に疑問です。
念のため申し上げておきますが、ここで申し上げているのは、理由の二つ目として次に申し上げる、「社外取締役には、そもそも経営陣に対等に議論できるだけの情報が与えられていない」という問題とは異なり、個人の資質の問題です。どんなに豊富な情報が与えられていても、自らの立場や地位を考えて経営陣に忖度するような人間は社外取締役には不適格ではないかということです。
多くの上場会社が社外取締役の確保に苦労する中、現在は社外役員専門のヘッドハンティング会社が存在し、多くの社外取締役や社外監査役が登録していると聞きますが、そのようなエージェントを使ってまで社外取締役になろうと指向している人たちが、めでたく自分を採用してくれた会社及び経営陣に対して、自分の立場が危うくなりそうなときであっても、何ら忖度せず忌憚なくものが言えるかどうかについて、正直私は懐疑的です。そしてこのようなメンタリティの社外取締役をどんなに増やしても、その会社のガバナンスが増進されることなど期待できないような気がします。
「社外取締役が増えれば会社のガバナンスは良い方向に向く」というテーゼが全く検証されていないと考える二つ目の理由は、端的に言えば、「月に一回、取締役会にだけ出席する以外に出社もしない社外取締役が、ガバナンスに貢献することなど、そもそも不可能なのではないか」ということです。「いやいや、オレは月一回どころではなく、もっと頻繁に出社しているぞ、指名委員会等のメンバーでもあり、頻繁に幹部候補者と面談もしている。何を言っているのだ。」などと仰る方もいらっしゃるでしょう。ただ、私が申し上げようとしているのは、そのような枝葉末節の話ではありません。
「Board 3.0」という議論があります。
これは2019年に米国で提唱されたもので、その概要は以下のようなものです。
すなわち、現在の取締役会(Board 2.0)がモニタリング・ボード(「Monitoring Board」要するに業務執行の監視監督を主たる役割とする取締役会のことです)へと変容してから40年ほど経過するが、その間の企業規模、業務の拡大、企業活動の国際化、市場環境の複雑化に、パートタイムで月に何日かしか会社に行かず、取締役会の審議対象事項についての情報収集は全面的に会社事務局に依存し、しかもキャリア終盤にあり自身の名声に傷がつくことを恐れてリスクテイクに躊躇する社外取締役は到底対応しきれない、よってそのような社外取締役が会社に何人いようとも、モニタリング・ボードとしての経営の監督機能は十分に発揮できない、との問題意識を前提とし、資本市場で活動するアクティビストや、プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)等の方が遥かに投資対象会社の経営状況を詳細に把握している、そのようなPEファンドのガバナンス・モデルを、総ての会社に導入させるべきではないのか、概略そのような議論です。
この議論は、若干誤解されているところはありますが、その本質は、PEファンドから社外取締役を送りこむべきという点にあるのではなく、社外取締役による業務執行の監督機能を十全に発揮させるには、社外取締役に、取締役としての職務により深くコミットさせ、業務執行取締役と同様の情報を会社から得られるようにする一方、より多額の長期報酬を前提に強大な権限と責任を付与し、同時に会社のサクセッション・プラン(後継者策定プラン)にも深く関与させることが必要であり、そのようなコミットメントは、まさしくPEファンドのマネージメント・モデルではないか、そうであれば、彼らのマネージメント・モデルを参考にして社外取締役制度を見直したらどうか、という点にあります。
我が国でも、現在の社外取締役の在り様は、まさにBoard 3.0が問題視する状況にあるように見受けられます。取締役会は、多くの会社で、会社の意思決定事項を執行側が説明し、社外取締役のご託宣を承る場になっており、会話が一方通行になっている会社が非常に多く、業務執行取締役の社外取締役への過度の忖度の結果、業務の実態を理解しない筋違いの指摘やコメントも無視できず、無駄な時間と労力がかかっていると言わざるを得ない実態が指摘されています。
更に業務執行取締役にとってみると、総ての議案は既に社内の(社外取締役が出席していない)執行役会または経営会議等で議論が尽くされ、社内合意が既に形成されているため、取締役会で自らの意見を述べることは難しく、またその必要もありません。このような実態があるにもかかわらず、社外取締役からは、取締役会での社内取締役の発言がなく、活発な議論がなされていないなどと批判されることも多いと仄聞します。
いずれにしても、日本の多くの会社では、取締役会で会社の意思決定や経営方針等について、社外取締役を加えて実効性のある議論が行う素地そのものがないように思うのです。一言で言うと、実業はそれほど甘くない、それに尽きるように思います。
お上が右を向けと言えば一斉に右を向くのは、ある面日本人の美徳ではありますが、ことガバナンスに関して、形式的に社外取締役を増員し、まして一定割合を女性にせよなどという、OECDの風潮に乗っただけのお上の押し付けを形式的に遵守し、それをガバナンスと称して制度だけ形式的に変えることなど、実は会社にとっては寧ろ害悪以外の何物でもない、それが真に会社のためになるなど、実は誰も信じていないのではないか、ぼくは最近そう感じています。(誤解されては困りますが、ぼくは米国留学時代をきっかけにして、女性の能力をもっと生かすこと、そのための社会環境を整備することこそが我が国に最も必要な変革だと信じてきました。それは今でも全く変わりません。それと、お上から形式上女性管理職を何パーセントにせよ、という命を受け、その数値目標の達成に汲々とするということは全く異なるということです。)
「稼げる国ニッポン」だの「新資本主義」という単なるキャッチコピーを乱発して社外取締役という特権階級を作り出したのはよいが、その流れに乗るためだけに制度を変える会社、さらにはその特権階級にしがみつくためにヘッドハンティング会社にまで登録して社外取締役という役職に固執する老人たち、そんなものが全く機能していないことは、最近話題になった損保各社のカルテルや小林製薬の紅麴問題が端的にあぶりだしているように思うのです。
ちなみに、この議論に関して社外監査役について除外したのは、監査役であれば、会社もこちらが要求した情報提供は拒めませんし、その気になればCEOなど、社外監査役が問題点に切り込んでいくことにメリットを感じる人を巻き込んでいけば全容を明らかにすることはできるからです。要は、監査役業務は業務執行とバッティングしないので、その嗅覚次第では十分に会社に貢献できると思います。片や社外取締役の場合は、業務執行そのものを深く理解しないと何も貢献できず、そこは嗅覚の問題というよりは、まさしく会社業務への理解の深度の問題ですので、両者は本質的に異なると思っております。
2024/07/03